死せど前に進みたいのに “How to Say Goodbye”
タイトル画面の供花、ヤマユリの美しさと、その後求められる入力内容への感情の高まりがピークだった。
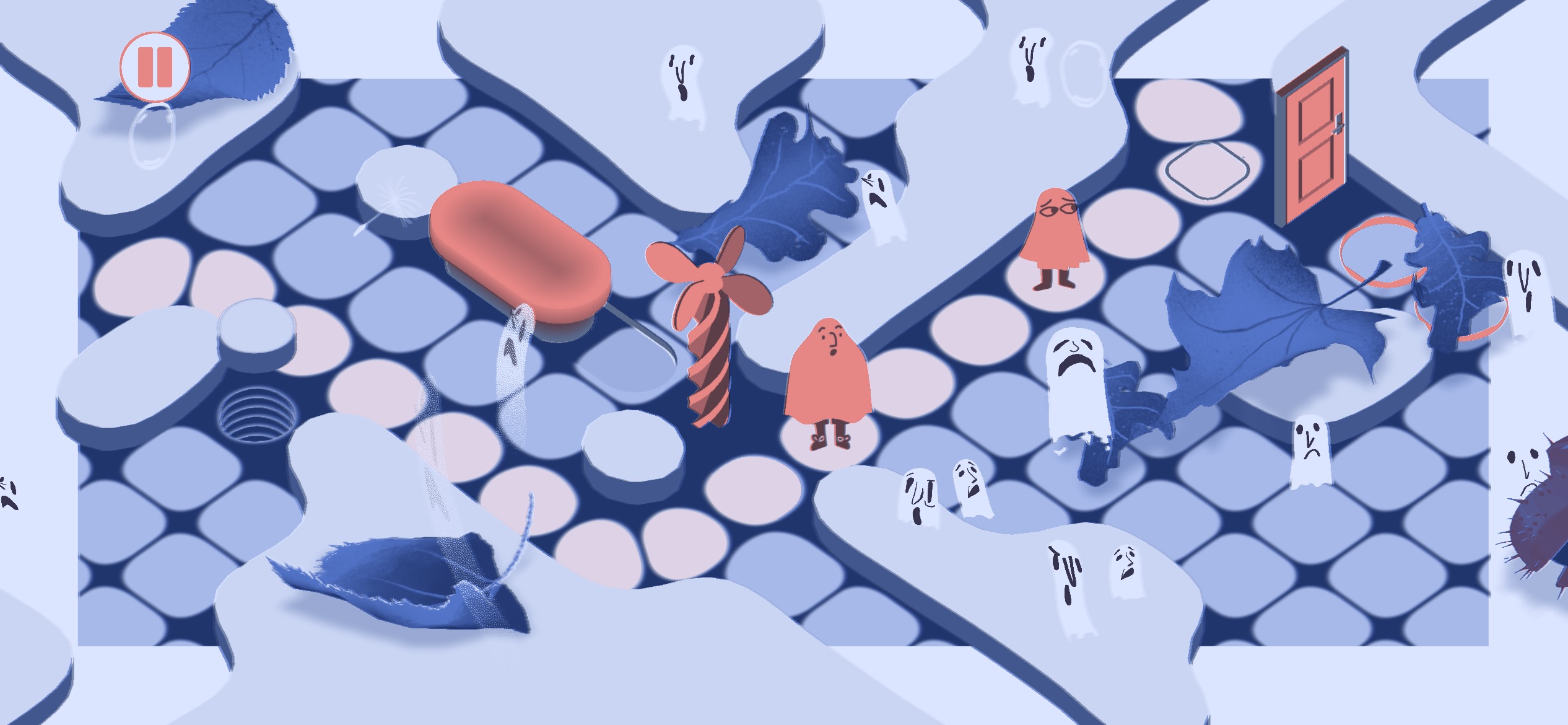
トレーラーが非公開になっていたため画像に差し替え。
この世とあの世の狭間、道が奇妙に曲がりくねる不思議な世界を幽霊たちが旅するスライドパズル。
列全体が動き接続点でループするというスライド方式だが、このパズルは選択したパネルと動かす方向によってスライドの列が障害物に沿って蛇行するというルールを持つ。これによって、スライドの仕方に依存した不規則な2点が繋がるというユニークな挙動を見せる。
旅する幽霊たちの目的地に揃って辿り着くことでクリアとなる。ほとんどの場合は最初から明らかな扉だが、時に長い距離を移動したり、あちこちの扉を行き来することもある。
いくらでも邪悪になれるルールではあるが、中身は非常に簡単だった。
全体が動くスライドパズルでは別の列との兼ね合いを考えなければならないことが多いが、このパズルはそうではなく、基本的に動かしたいパネルとその目的地とを1個ずつ合わせていくだけで片付けられる。
結局マヌケは最後までスライド列の生成法則を把握できなかったが、別の列への影響を考える必要がないほど簡単なことや概ね直感通りに動いてくれることもあって、ルールが正確にわからずともそれほど悩まされることはなかった。
だが長所といえばせいぜいその程度で、このパズルはクソゲーだった。
難易度の低さは、スライドパズルでありながら従属のもどかしさが全くないと書けば、パズルの奴隷の傾向からして短所にもなり得たはずだが、それを長所として扱いたくなるほどに酷いのだ。
あくまでわからずとも支障がなかったというだけで、最後まで正確な内容が掴めないようなわかりにくいルールはただただ面倒なだけだった。
また、このパズルは道を塞ぐギミックとしてボタンやスイッチを導入しているが、これらの影響を受けるパネルと同列に並ぶことがしばしばあり、それによって元の状態に戻せなくなることがある。1手前の状態に戻すのに1手では足りない遠回りをさせられることがあるだけでなく、時には詰んでしまうことさえある。
直感的なわかりやすさを特徴とすることの多いスライドパズルにあるまじきルールのわかりにくさといい、パズルの奴隷がスライドパズルにおいて最も重んじる対称性を壊すリスクといい、スライドパズルとしての面白みは欠片もなかった。
さらに、このパズルにはより酷い欠点が存在している。それはスライドの操作性である。
目的のパネルを選ぶこと、目的の方向にずらすこと、目的の位置で止めることと、基本とも呼ぶべき三つの動作の全てが思い通りにならないのだ。何度別のパネルに判定を吸われただろうか?何度スライドが引っかかっただろうか?何度目的地の前後のパネルに止まってしまっただろうか?
一つだけでもストレスなのに、三つ全てがままならないのだから抱えた苛立ちは計り知れない。
等角投影の視点だからか、あるいはプラットフォームの問題か、はたまたその両方が原因だろうか。少なくともiOSではトレーラーのようなメリハリの付いた流れるようなスライドは不可能である。
そもそも、制作者が真に作りたかった遊びがパズルだったのかどうかは疑問が残る。
ゴールを遠ざけてあちこち探させたり、視界の邪魔にしかならない飾りに物理演算を使ってまで無駄に判定を作り、あまつさえその下にギミックを隠したりなど、複雑なスライドのルールと併せて考えると、パズルというより迷路やかくれんぼでもさせたかったのかもしれない。
パズルの奴隷としてはことごとく腹立たしいやり方ではあるが、ゲームと狭間をさまよう幽霊たちの物語に繋がりを持たせるための選択だとすれば理解できる。
しかしながら、この作品はパズルだけでなくストーリーも酷いので、たとえパズルがストーリーの犠牲だったとしても、結果的にはただの共倒れでしかない。
ストアの説明文や登場人物の名前などからわかる通り、このストーリーは絵本のような物語を描くことを目標としていたのだろう。だがこの作品は、少ない文章と絵で無限の行間を描く絵本のような、そういった奥深い物語を持たない。あるのは説明不足で単調でありきたりな、退屈な物語だ。
ゲームを始めると、自分の名前ではなく亡くなった親友という名目でなんと他人の名前の入力を求められ、どうしたものかと悩みながらもこれはナラティブな物語が待っているのかもしれないと心躍ったものだが、ここで入力した情報が生かされる場面はなく物語も画一的で、悩んだ時間はただただ無意味でしかなかった。ニックネーム、好きな食べ物に飲み物に季節と書き記すべき項目は詳細だが、そのどれもが物語において飾り以上の機能を果たすことはない。
この物語の主人公は人柄や来歴といったパーソナリティが固定されたキャラクター、Toveであり、彼女を取り巻くのもまたパーソナリティが固定されたキャラクター達である。この名付けられたキャラクターはToveの行動原理であり心の支えという位置付けだが、そこに至るまでの経緯や一部の家族構成が固定されているため、この物語に創造されたパーソナリティの入り込む余地はない。
また、パーソナリティで埋めたはずのストーリーすらも前後の繋がりがない場面が目立つ。Wizardのことや、その居場所を探す話が一体どこで説明されたのか?Sendakが落ち着きを取り戻したのはなぜなのか?全編英語ゆえに英語音痴のマヌケが読み取れなかったこともあるだろうが、行間で補完するには難しい唐突な展開は呆然としてしまう。
さらに、これらの物語は全て味気のないナレーションで行われるため、前述の不連続な展開も相まって、演出の起伏のなさに読み進める気力は失せていく一方だった。
これはまるで電子書籍化した絵本を付属させたゲームである。そしてそのどちらもが面白くない。
絵本風ゲームを目指して失敗したという見方が自然だろうが、私の抱えた苛立ちからすれば絵本風を言い訳にしたクソゲーである。
ネタバレ項目: him and her
狭間を抜け出せないながらも悪霊に堕ちることを拒み前向きであり続ける主人公Toveと、悪霊を生み出す元凶とされる黒幕Wizard。Toveはshe、Wizardはheで表されるが、はたして彼らが赤の他人なのかは疑問が残る。
Wizardの素顔は女性のものであり、またChapter Elevenで見られる魔術師が映り込んだかのような壁の絵はToveによく似た目元を光らせている。
元は一つの存在で、大切な人の死を前に前向きになろうとする心と後向きであろうとする心とで割れてしまい、手段は違えど互いに傷つけ合っていたことを認め、墓前で二人揃って死を受け入れることで、Toveはようやく狭間からの脱出を迎えたのだろう。
だが単調な演出に前後の繋がりが薄い展開のせいで、マヌケはToveのことを誤解してしまった。マヌケの目には、Toveはしばらく無愛想な傍観者として映った。彼女が名付けられたキャラクターを救おうとするのはあくまで親切に対する礼節に過ぎない、と。
Chapter Fourでの雨宿りで記憶を取り戻した通り、彼女が名付けられたキャラクターに対して特別に入れ込む理由はあるのだが、逆にそれしか説明がないせいで、彼女に手を貸す他の幽霊たちに対して素っ気ないのではないかと、Sendakの喪失は彼女の心に何も残さなかったのかと、その扱いの軽さに冷たさを感じた気持ちの方が大きくなってしまった。
おかげでChapter Fifteenの問答はいつの間にか達観しているかのようでわけがわからなかったし、Chapter SixteenでToveの第二の死を目の当たりにした時はWizardとの対話がそんなに大それたことだったのかとまるで理解が追いついていなかった。
誤解が解けたのは、名付けられたキャラクターの入力内容をいくつか変えてプレイした2周目を終えてからだった。
ほとんど変化のない物語はひたすら退屈で仕方がなかったが、Toveに対する誤解が解けただけやる価値はあった。
余談: 名付け
家族、親友、恩人……失えば悼むであろう大切な存在はマヌケの人生の中で様々な人物が思い浮かぶが、食べ物、飲み物、季節の好みを全て把握した人物なんて一人も思いつかない。さらにニックネームまで要求してくるのだからハードルが高い。
誰を差し出したとて差し出すだけの価値が物語にある保証はなく、またあらかじめ与えられる設定の生々しさとこの行為の空々しさに、最終的にマヌケはもう使わなくなった大昔のHNを差し出して供養とした。
このパズルで悩んだ時間よりもはるかに長く悩んだと思う。結局、それは全て無駄な時間でしかなかったわけだが。
迎えた末路も悪霊化に消滅とまるで救いがない。とうの昔に死んで久しい存在とはいえこんな結末はさすがに望んではいなかった。
本当に、真面目に考えたのが馬鹿馬鹿しくて仕方がない。