神の手を選ぶのは自らの手 “One More Button”
私はパズルの奴隷。あなたはゲームの奴隷。
“No More Buttons” から続くシリーズ作品の2作目。
コントローラーが画面上のイラストのタップに制限される基本ルールはそのままに、前作の2Dプラットフォームパズルアクションから一転して、今作は見下ろし型の倉庫番ライクなパズルとなっている。
前作は主にカメラの移動に伴うイラストのフェードアウトにどう対処するかを考えるパズルだったが、今作は一画面に収まる問題として分割されているので、レベルデザインの枠組も考えるべき内容も変化している。
カメラを固定にした今作ではリスタートという名の回転ギミックと、規定の方向のブロックを乗せることで解錠するギミックの組み合わせによってイラストを隠している。
最初は4方向全てが揃っているが、解錠のためのブロックを工面しようとすると移動が制限されていくといった具合だ。1方向を潰してもクリアできる、または後で復活させられるように回すブロックの順番やどこから押すべきかを考える必要がある。
他にも面ごとに決められたテーマがありそれに沿って制限がかけられたりする (例えば滑る床のギミックであったり、視界を狭めることで擬似的に前作のようなカメラ移動によるフェードアウトへの対処を求めたりといったようなこともある) が、やはり基本は潰した1方向分の操作をいかにカバーするかだろう。
しかしながら、このパズルは基本で終わっていてそれ以上の応用を求めていないため、前作同様簡単に終わってしまう。
解決すべき事柄の層が薄くて単純と言えばいいだろうか?目の前の問題を解決するために何をすべきかを考えた場合、ある手立てを取ると何かが干渉する、解決後に別の障害が浮上するなどといったねじれがない。
前作よりもパズルらしくはなったものの、せっかくのパズル向けの基本ルールが生かしきれていないという気持ちは今作でも同じだった。
そして改めて思うのが、配置がバラバラの方向キーはそもそも遊びにくいという不満である。
やるべきことは見えているのに思い通りに動かせない苛立ち、操作を誤った時の疲労感といいあまり気持ちのいいものではない。
こんなに遊びにくいにもかかわらず、なんと今作にはスニーキングの要素がある問題が存在する。具体的な索敵範囲もわからないのに、思うように動けないながらもそれでもなんとか動かなければならないストレスは大きかった。
パズルの内容にはあまり関係ないが、前作とは違い今作のストーリーでは何かしらの強いメッセージを感じることはできなかった。
アナログコントローラーがいかに偉大な存在であるかがテーマだったなら、わざわざストーリーにするまでもなく前作の時点で既に自明なことだったと思うのだけど。
今作が本当に伝えたかったこととは一体何だったのだろうか?
追記
Steamでのリリースに伴ってか、secret levelsおよびsecret endingの追加をはじめとした大型アップデートが行われたので、それに関する追記。
なお、今作は最新版 (Ver. 3.0.2) に至るまでにVer. 2.0.2というメジャーアップデートを挟んでいるのだが、マヌケはそれについて詳細まで確認していなかったため、Ver. 1.0.9との比較になることをあらかじめ断っておく。
点線で表されたムービーの存在に、secret endingのためには何かしらの条件を満たさなければならないのはわかるものの、変わったことといえばWorld 8に新しい問題が一つだけポツンと追加されただけで、クリアしたところで何かが変わった手応えもない。
secret levelsと複数の問題の追加を示唆する以上はまだ何かがあるに違いないと思いつつも、久しぶりのプレイでその手がかりを簡単に掴めるはずもなく、結局マヌケは一からやり直すことにした。
6年も前のことを正確に覚えているはずもないマヌケ、再プレイはかつて自分が苦戦しなかった印象を信じて臨んだのだが、意外なことにマヌケは中盤まで苦戦した。
自分の頭が愚かになったことを認めたくなかったマヌケは真っ先に問題の改定を疑い、実際いくつかの問題は確かにレベルデザインが変わり明確に難化していたのだが、顕著なのは最序盤だけだった。Ver. 2.0.2で追加されたであろうアンドゥ・リドゥブロックの存在を考えると、本来ならむしろ易化してしまった問題のほうが目立つはずなのではないだろうか。
慣れてしまえばさほど苦労しなくなるのは昔と同じ印象だが、そもそも後半のレベルデザインが総じて簡単なので、慣れる頃には歯応えのあるパズルがなくなっている、というのがかつて簡単という印象を強く残した原因のように思える。
とはいえ、不満は昔と変わることなくそのままだった。
レベルデザインは改定してもスニーキングはそのままで、ブロックの隙間を縫って視界を通してくる腹立たしい仕様も相変わらずである。
それに、やはり散在したボタンはそもそも操作しにくく気が散るため、レベルデザインの如何によらずこのシステム自体が好きになれそうにない。
ちなみに今回、ブロックによる開錠が反応しないことが何度かあった。過去に同様のことがあったかどうか記憶がないが、アンドゥ絡みのバグだろうか?
その他、パズルには関係のないところではあるが今回大幅に変わった要素として、全体的に色使いがシンプルになり線が滑らかになったという画風の変化がある。
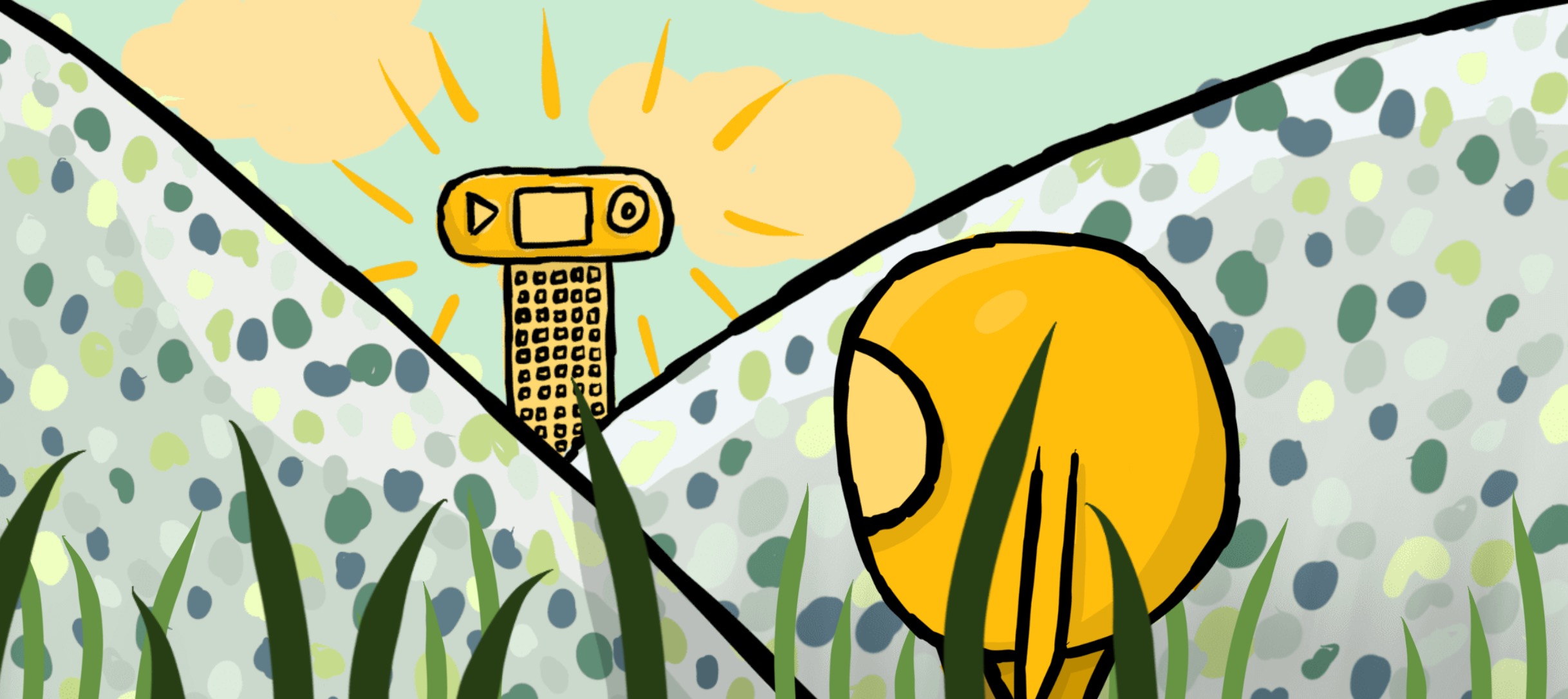

私は昔の荒いデザインのほうが好きだった。
タイトルロゴの浮きっぷりやローフレームなアニメーションに似つかわしくない滑らかすぎるモーフィング、さらには全ての線が滑らかになったわけではないという統一感のなさからしても、新しいデザインは総じて中途半端にしか見えなかった。
ネタバレ項目: secret levels & ending
再プレイしてみてもエンディングが変わらず、一体何を見逃したのだろうかと途方に暮れ、だが怪しいものといえば新しく追加された問題しかないと、マヌケはその問題で試行錯誤することでようやく隠されたWorldへの入口を見つけることに成功した。
ポーズ画面のステージセレクトに戻るボタンがヒントだっただろうか。赤色の強調に早期から何らかの示唆を疑いながらも、結局正しく気づくまでには随分と時間がかかってしまった。
下向きのコマ送りボタンが機能した瞬間は一定の感動が生まれたものの、上向きのコマ送りボタンがポーズ画面と同等の機能をした時点である程度確信できていたので、いくらか予定調和になってしまっただろうか。
そもそもアンドゥ・リドゥはレベルデザインに組み込むものではなく便利なシステムツールとしての印象が強く、Ver. 2.0.2で追加された時もそういう触れ込みだったのではなかったのではないかとか、ならばタイトル画面やステージセレクトの左右ボタンはなぜ未だ特別なのだとか、赤と黄の色分けが結局強調以外の機能的な意味を持っていないではないかとか、結果的にはsecretに対する感動以上にシステムをメタに組み込む上での定義の甘さに対する釈然としない思いのほうが大きくなってしまった。
肝心のsecret levelsの内容、アンドゥ・リドゥブロックによる履歴処理を利用したギミックも、ある程度は直感的に納得できるものの、全てを理解して使いこなすにはややこしく、面倒くさいという印象が強く残った。
どのタイミングで履歴が取られるのか、赤と黄とで絡み合わせた場合どうなるのか、ブロックが重なった場合やリトライボタンが絡んだ場合の履歴の扱い方はどうなるのかなど、大雑把に動かす分には思い通りになっても、刻んだ履歴が細かくなるほど思い通りにならないルールの読めなさに頭を抱えることが多くなる。
結果的に、マヌケは1手ずつずらしながら抜け道となる履歴が見つかるのを待つという身も蓋もない解法に落ち着いてしまった。レベルデザインがよく練られねじれていることはわかるものの、勘に頼ったような表層的な理解のまま解き進めたマヌケが然るべき達成感を得られるはずもなかった。
ちなみに、ストーリーはsecret endingまで見てもやはり意味がわからなかった。
全編通して赤が主人公にとって仇なす存在であることはわかりやすくなっているが、赤でも黄でも結局隷属関係なのは同じではないのだろうか?
同じ奴隷でも、新しい環境に無理やり順応させられるよりは馴染みのデバイスの方がいいということなのか……。